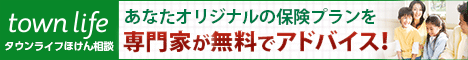こんにちは、ヤス@ロコ父さんです。
会社関係の退職手続きを除いて
「退職日までにやっておけば良かったなぁ」
と思う事が幾つかあります。
まぁ退職前の1ヶ月間は会社関係の退職書類を記入して提出したり業務引継ぎをしたりと、そんな事にまで頭が回っていなかったです、私の場合は(笑)。
それから、退職後の1ヶ月間も、雇用保険の申請だとか国民健康保険・国民年金の申請などで頭が一杯でした、私の場合は(笑)。
それで以下3点が「私が退職日まで(つまり在職中)にやっておけば良かったと思うこと」です。
1.銀行口座の追加
2.証券口座の追加
3.クレジットカードの追加
退職後には銀行口座を追加で開設
ご存じの通り、お金を預けている銀行に万が一のことがあった場合に預金が保護されるのは1,000万円までです。
一方で30数年もサラリーマンをしてきた中高年が特別優遇制度を使って早期退職すると、退職金の特別加算(割り増し退職金)もありますから、退職後に振り込まれる退職金総額は預金保護の限度額を軽く超えてしまいます。
私の場合は住宅ローンでつきあってきた金融機関に一括で振り込んでもらったのですが、預金保護の限度額を遥かに超える額が1箇所の銀行口座に集中しているのは、あまり気分の良いものではありません。
結局私は、退職して1ヶ月後くらいに新しく銀行口座を開設しました。
今のおススメは、
です。
普通預金でも年利 0.2% の金利がつきます。
変動金利が嫌なら1年定期預金に入れてしまえば、固定金利の年利 0.2% となります。
その他に、
- 楽天銀行
- 新生銀行
などもおススメです。
まとめ:
退職するまでの1ヶ月間で、新しい銀行口座を開設しておくと良い。
(できれば退職金特別プランの内容が良いと思う銀行に)
そうすれば、退職金を振り込んで貰う時に、あらかじめ分散して振り込んで貰えるように調整が可能ですので、振り込み手数料が節約出来たり、ATM間を行ったり来たりする面倒な手間が省けます。
退職後には証券会社の口座も追加開設
退職金を一旦は銀行の口座に入れて大部分は定期預金に預けておくのが王道ではありますが、それだけではお金は全然増えません。
※ せいぜい年間で数万円の運用益(利息)
そこで金融資産の1/3くらいは、投資信託・個別銘柄株式・ファンドラップ(お任せ投資信託)で運用するのも良いと思います。
今のおススメは、
です。
結局、今まで付き合ってきた証券会社とは別に、退職して1ヶ月後に楽天証券の口座を開設しました。
「企業型DC ⇒ iDeCoの移換先として」が主な使い道ではありましたが。。
私の場合、メインバンク(銀行)のファンドラップを300万円(退職金特別プラン)ほど購入しましたが、それに加えて楽天証券では個別銘柄(※)を幾つか購入しました。
※ 国内株式・東証一部上場企業・バリュー株
これで金融資産の1/3くらいが投資信託・ファンドラップ・個別銘柄株式に割り当てている状態となりました。
※ この1/3の部分は「タイミングによっては最悪 50% Down になっても仕方がない」と「覚悟を決めて」やっています
3年~5年単位の長い目で見れば年間運用利回り 5%~10% くらい は期待(※)できそうです。
※ もちろん20%くらいの銘柄はロスカットする必要も出てくるでしょうけど。。
定期預金に預けた場合の利子の30倍くらいの運用益が期待できることになります。
※あくまでも期待です
まとめ:
退職するまでの1ヶ月間で、新しい証券口座を開設しておくと良い。
(企業型DCをやってきた方は、iDeCoの運用コストが安い証券会社に)
- 企業型DCをやってきた方は移換先(iDeCo)として利用できる
- iDeCoの運用指図だけをするとしても運用コスト(管理手数料)が安い証券会社が選べる
- 投資信託のバラエティも豊富になる
クレジットカードの追加は退職前にやりましょう
世間では「芸能人や自由業の人はクレジットカードが作りにくい」とよく言われていますが、30数年間サラーリーマンをやってきているとこの事をつい忘れてしまいがちです。
私も普段使うクレジットカードは2-3種類あるので、当座の生活には何の支障もありませんが、
- いざ退職後に「楽天カードをつくってみたい」
と思ってネットで申し込もうとしても「無職」だと審査が通りません。
退職して無職になる前に、
- 追加で開設する「銀行口座」あるいは「証券口座」とセットで考えてみて
- 新しいクレジットカードを1枚作っておく
と、後から「しまった~」とならずに済みます。
まとめ:
退職するまでの1ヶ月間で、新しいクレジットカードを作っておくと良い。
(新しく開設する銀行口座か証券口座をセットで考えて、ポイントなどでメリットが出るように)
以上ご参考になれば幸いです。